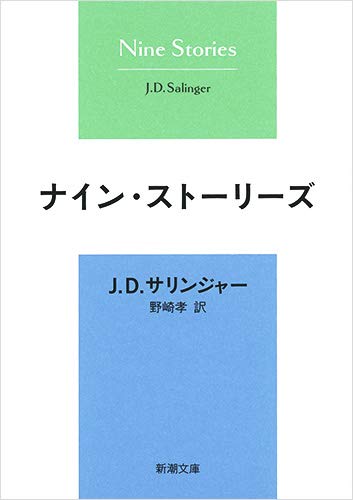2023/03/20
『書店主フィクリーのものがたり』(ガブリエル・ゼヴィン:著/小尾芙佐:訳/ハヤカワepi文庫)を読んだ。
まずは出版社の紹介文を引く。
その書店は島で唯一の、小さな書店―偏屈な店主のフィクリーは、くる日もくる日も、一人で本を売っていた。かつては愛する妻と二人で売っていた。いつまでもそうすると思っていた。しかし、彼女は事故で逝き、いまはただ一人。ある日、所蔵していたエドガー・アラン・ポーの稀覯本が盗まれる。売れば大金になるはずだった財産の本が。もう、なにもない、自分にはなにも。それでもフィクリーは本を売る。そしてその日、書店の中にぽつんと置かれていたのは―いたいけな幼児の女の子だった。彼女の名前はマヤ。自分も一人、この子も一人。フィクリーは彼女を独りで育てる決意をする。マヤを育てる手助けをしようと、島の人たちが店にやってくる。婦人たちは頻繁にマヤの様子を見に訪れるし、あまり本を読まなかった警察署長も本を紹介してくれと気にかけて来てくれる。みなが本を読み、買い、語り合う。本好きになったマヤはすくすくと成長し…人は孤島ではない。本はそれぞれのたいせつな世界。これは本が人と人とをつなげる優しい物語。
人には何かしら悲しくて仕方がない事があるものだ。それはたいていその人にとって大切な大切な記憶だ。だからこそ記憶は決してなくならない。色褪せもしない。悲しくて悲しくてしかたがないからこそ、大切に大切に心の奥底に仕舞っている。この本はそんな人たちの物語だ。悲しみに溢れている。しかし悲しみと同じだけ、いやそれ以上に思いやりがある。慈しみに溢れている。捨て鉢にならず、まわりの人への思いやりと優しさを忘れなければ、いつか幸せは追い求めなくても向こうからそっとやってくる。ほんとうの幸せとはそうしたものだろう。人生は捨てたものじゃない。これはそんな物語だ。
本書の各章のタイトルは以下のとおり。それぞれが古今の傑作短篇小説のタイトルである。参考までにその短編が収められている本がわかったものについては、amazonへのリンクも貼り付けておく。
【第一部】
- 「おとなしい凶器」(ロアルド・ダール)
- 「リッツくらい大きなダイアモンド」(F・スコット・フィッツジェラルド)
- 「ロアリング・キャンプのラック」(ブレット・ハート)
- 「世界の肌ざわり」(リチャード・ボーシュ)
- 「善人はなかなかいない」(フラナリー・オコナー)
- 「ジム・スマイリーの跳び蛙」(マーク・トウェイン)
- 「夏服を着た女たち」(アーウィン・ショー)
【第二部】
- 「父親との会話」(グレイス・ベイリー)
- 「バナナフィッシュ日和」(J・D・サリンジャー)
- 「告げ口心臓」(E・A・ポー)
- 「アイロン頭」(エイミー・ベンダー)
- 「愛について語るときに我々の語ること」(レイモンド・カーヴァー)
- 「古本屋」(ロアルド・ダール)
以上が各章のタイトル(名作?短編小説の題名)である。そのそれぞれについて主人公・フィクリーが養女・マヤに宛てた一言が添えられています。これがイイ! 娘に向けた慈愛がにじみ出ている。子を育てるとはどういうことだろうか。かたちの上では子は親から与えられるばかりだ。しかし、親は子を育て何かを授けることで逆に何かを得ているのではないか。それは何かで価値を計ったり、何かに代えたりできないとてつもないものだ。うまく言葉にできないが、子を育てたことがある私にはそれが確かなものとしてわかる。それはあらゆるものを凌ぐ幸福感、それが得られたからには命を失っても惜しくはないほどの幸福感だ。この物語は人生の無常を描きつつ、人は無常の中にも幸福を見いだすことができることを我々読者に教えてくれる。
「もしあなたが本を読むことが好きならば、ぜひこの本を読むことをお薦めします」 本書を読み終えた今、私はすべての本好きにこう勧めたい。
最後に、本好きの心をグッとつかみそうな言葉をいくつか書きとめて記憶に残したい。
きみは、ある人物のすべてを知るための質問を知っているね。あなたのいちばん好きな本はなんですか? (本書P121より)
本というやつは、しかるべきときがくるまで、読み手が見つからないことがあるんだね。 (本書P128より)
本屋としては、賞をかちとることが、セールスにはかなり重要だが、小説の質に関しては、それはほとんど関係がない。 (本書P251より)
「あたしの故郷の町には本屋が一軒もないの、知ってた?」
「ほんとうに? アリスなら、一軒ぐらいなきゃいけない気がするけどね」
「そうよ」とニックはいった。「本屋のない町なんて、ほんとうの町じゃない」
そこでぼくたちは大学院をやめ、彼女の信託基金をとりくずしてアリスに引っ越し、のちに<アイランド・ブックス>となる本屋を開業した。
(本書P266より)
「いいかい。本屋はまっとうな人間を惹きつける。A・Jやアメリアみたいな善良な人間をね。おれは、本のことを話すのが好きな人間と本について話すのが好きだ。おれは紙が好きだ。紙の感触が好きだ、ズボンの尻ポケットに入ってる本の感触が好きだ。新しい本の匂いも好きなんだ」 (本書P335より)
私の住む町には本屋が一軒もない。ほんとうの町じゃない。悲しいことに。